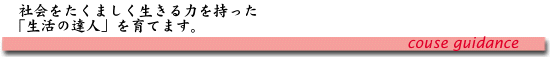 |
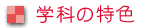  社会や文化、生活などあらゆる分野での激変が、世界的な規模で予測される21世紀。多くの場面で人の生き方が問われる時代にあって、自分の個性を活かしながら社会生活を送る、そんな魅力的な女性の育成が生活社会科学科の目標です。 社会や文化、生活などあらゆる分野での激変が、世界的な規模で予測される21世紀。多くの場面で人の生き方が問われる時代にあって、自分の個性を活かしながら社会生活を送る、そんな魅力的な女性の育成が生活社会科学科の目標です。法学・政治学・経営学・経済学を、生活者の視点からトータルに研究する生活社会科学科。人間の生活の基盤となる分野を、幅広い視野から科学的に検証します。分野を絞って学ぶのではなく、現実の社会を構成するあらゆる側面を総合的に解明するのが目的のため、カリキュラムの内容は幅広く多彩。 1年生の入門ゼミをはじめ、授業スタイルの多くが、教員と学生が自由にディスカッションし、双方向で授業を進める少人数制のゼミナール形式。のびのびとした雰囲気のなか、各分野から集まったさまざまな教員と交流できます。総合的に学ぶことで、将来の選択肢が大きく広がるのもこの学科の魅力です。 |
 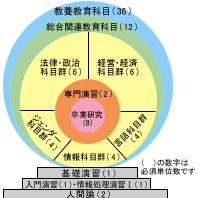 本学科での講義は、全学科共通課目(人間論)、教養教育科目、総合関連教育科目、専門教育科目の4つからなります。学生は、4年間を通して、これら4つの科目にわたり幅広く学習することが求められますが、言うまでもなく、学科での重点は専門教育科目に置かれています。 本学科での講義は、全学科共通課目(人間論)、教養教育科目、総合関連教育科目、専門教育科目の4つからなります。学生は、4年間を通して、これら4つの科目にわたり幅広く学習することが求められますが、言うまでもなく、学科での重点は専門教育科目に置かれています。専門教育科目は、暮らしと社会を科学する目を養うためのコアとなる「法律・政治」、「経営・経済」という2つの科目群と、そのための基盤となる「情報」、「言語」、「ジェンダー」の3つの科目群から なっています。それぞれの科目群を、基礎から専門へと段階的に履修できるように、1年生から4年生にかけて配列されています。これらの中には、「演習・ゼミナール」があり、そこでは、先生と少人数の学生が自由なディスカッションを通して双方向で専門テーマについて学ぶことができます。 |
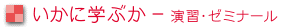 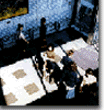 本学科での学習にとって、演習・ゼミナールは大変重要な役割を持っています。演習は学科専任の教員が担当し、一名の教員と20数名までの学生によって構成されます。
ここで、それぞれのテーマに即して研究・討論を集中的に行い、その成果を発表し、レポートとしてまとめます。 本学科での学習にとって、演習・ゼミナールは大変重要な役割を持っています。演習は学科専任の教員が担当し、一名の教員と20数名までの学生によって構成されます。
ここで、それぞれのテーマに即して研究・討論を集中的に行い、その成果を発表し、レポートとしてまとめます。演習は、1年生の「入門演習」から始まり、2年生の「基礎演習」、3年生の「専門演習A、B」へと進んでいきます。そして、最後に、4年生の卒研演習となります。 学生は1年生から必ず、いずれかの教員の演習に所属し、そこでの成果をもとにして、4年生になると、卒業論文(学士論文)をまとめることになります。演習の活動内容は、担当する教員によって少しずつ違うところがあります。 演習の大きな特徴は、一つは、参加者が比較的少人数なので、先生と学生間、および学生相互間で自由に議論し、自分の考え・意見を述べ合うことができることです。 とくに、「基礎演習」と「専門演習」では、1つの演習に参加できる人数は10数名までと限られているので、先生を含めて参加者同士の結びつきは強くなります。演習の中心はもちろん勉学ですが、それ以外にも、ゼミ旅行やゼミ合宿など、ゼミ単位の行事を計画することもできます。 ゼミ活動にどのように関わるかで、大学での生活も大きく変わってくるでしょう。 |